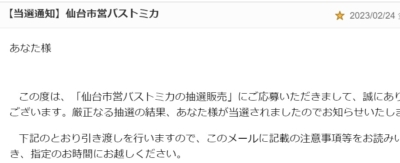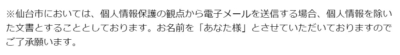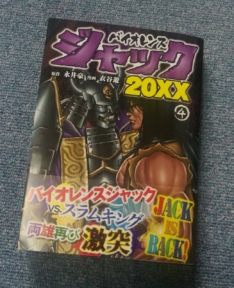SDガンダムの30周年を記念して刊行された『SDガンダムスペシャルアンソロジー』。
感想記事その2、ということでカラーピンナップに続いて
白黒ページのコミックとイラストの感想を書いていきたいと思います。
感想記事その1はこちら。
「SDガンダムスペシャルアンソロジー」 感想(その1)
https://tktkgetter.com/blog-entry-1470.html
○森本がーにゃ「森本がーにゃのSDガンダムいんふぉinヤンマガ」
本アンソロジーの最初を飾るのは「ガンダムインフォ」で紹介漫画などを掲載している
森本がーにゃ氏による「私とSDガンダム」的なエッセイ形式の作品。
この手のエッセイ漫画は共感できるかどうかでかなり印象が変わってしまうので
『フルカラー劇場』や『武者○伝』あたりの世代からちょっと外れてしまう自分にとっては
なかなか評価がしづらい作品ではあります。
「SDからガンダムに入っていった」点では同じなんですけどね……。
○森本がーにゃ「SDワールド入門4コマ劇場」
続く同氏の「SDワールド入門4コマ劇場」は
SDガンダムの柱とも言える騎士・武者・三国伝の3つを4コマ形式で紹介する作品。
ページ数の少ない中で4コマごとにオチも付けなくてはならない、という制約もあってか
各シリーズの中期の作品をかなりはしょってしまっている印象。
「SDガンダムいんふぉ」でも思いましたが
ナイトは『円卓の騎士』、武者は『天下統一編』あたりが幼少時の直撃世代である自分は
森本がーにゃ氏の世代から見ると抜け落ちちゃってるんでしょうね。
それとガンドランダーどこ……? ガンドランダーはどこなの……?
○今井神「SDガンダム妖怪大戦争!!」
『NEEDLESS』などで有名な今井神氏の作品は
女の子三人組が肝試しの最中にSDガンダムたちの騒動に巻き込まれる、という
今は亡きコミックボンボンの夏休み特集なんかでありそうな作品。
プラモデルや人間キャラを自由に合体させるシュールでカオスな
ドタバタ展開をはじめとした「何でもあり」っぷりがとにかく楽しい作品です。
全体的にポップな絵柄の中でやたらと気合の入ったブラックドラゴンの作画も印象的。
ラストのオチが弱すぎたのだけがちょっと残念です。
○貞松龍壱「SD頑駄無リアル形態紀伝」
漫画家やイラストレーターとして広く活躍する貞松龍壱氏の作品は
キャラクターに代弁させる形でリアル武者への思いを熱く語るという作品。
リアル武者や騎兵といった存在は否定意見も根強くあるので
「リアル武者大好き!」を全面に押し出してガッツリ描かれた本作は
けっこう珍しい視点な感じがしますね。
まあ例によって自分とは微妙に世代が違うのがネックですね。
見開きのνとサザビーの激突はものすごく格好いいんですが
これを「SD作品の可能性」と言われるとちょっと戸惑ってしまいます。
自分は騎士ガンダムシリーズでも騎兵や機甲神は大好きなんですが
暴竜神やゴッドカイザー、スペリオルカイザーまで行ってしまうと
なんか違うなあ、と思ってしまう部分はありますし。
○高田裕三「転生したらSDガンダムだった件」
80年代から現在もシリーズが続いている『3×3 EYES』などを手掛けている氏の作品は
ある意味タイトルの出オチ感が全ての異世界転生モノ。
転生者だからこそ知っている作品知識で敵を倒し
前世からの因縁にも決着を付けている、と30Pの短さながら
このジャンルに必要な要素をしっかりと押さえている作品なんですが
ぶっちゃけ「SD」である意味がほとんどないなあ、と思ってしまったり。
シチュエーションは1stガンダムの第1話をなぞったものですし
アムロやセイラさんなどの登場人物たちも普通に存在しており
出てくる機体もガンダムとザクとガンキャノンなので
「転生したらガンダムだった」ってタイトルで
リアル等身でやっても何ら変わりがない気がするんですね。
ラスト1ページの尻切れ感も含めて「異世界転生」というネタを
思い付いた時点で満足してしまった感があるので
SDガンダムである意味、SDでなければならない理由がほしかったです。
○岡本倫「ぼくが好きなガンダムNo.1」
『エルフェンリート』などの代表作を持つ岡本倫氏の作品は
大胆な俯瞰視点でのEX-Sガンダムのイラスト。
SDにしてはやや足が細目、長めに感じてしまいますがこれはこれで最近の流行ですし
氏自身がSD「風」デフォルメと称していますし
元々マッシヴなEX-SをSDっぽく落とし込むとこんな感じになのかもしれませんね。
ピンナップを除くとこちらが唯一のイラスト作品になりますが
氏は2019年時点だと週刊での連載を抱えていたので
スケジュール的な都合もあったのかもしれないなあ、と。
○森本がーにゃ「SD戦国伝 武神綺羅鋼 新凰頑駄無後日譚」
本アンソロではエッセイ、四コマに続いて三度目の登場となる森本がーにゃ氏による
「超SD戦国伝」の後日談を描く外伝作品。
氏のストーリー漫画は珍しいというか初めて読む気がしますね。
「SD戦国伝」の漫画は初期シリーズから全体的にハードな展開が多いですが
本作は日常や家族団欒などを中心にコミカルな描写も多く
導入部にあるような「平時の武者たち」の様子が垣間見える作品。
森本がーにゃ氏の丸みを帯びた絵柄もあって「優しい世界の武者たち」といった感じです。
○蒔島梓「Twilight AXIS meets G-ARMS」
『Twilight AXIS』を連載していた蒔島梓氏の作品は
『Twilight AXIS』の世界とGアームズの世界とが繋がる正統派クロスオーバー作品。
わずか8Pの作品のため作中で言われているような「せわしなさ」はありますが
次元の裂け目から別世界の人物たちが現れて
戦いの混乱の中で再び裂け目が開いて去っていく、という
クロスオーバーもののお約束の展開は受け入れやすいですし安心感がありますね。
真面目なキャプテンとR・ジャジャはいいコンビになれそうですし
マスクコマンダーとトリスタンは腹の探り合いをしてそうですし
もっと二つの世界のメンバー同士の交流が見たかったなあ、と。
最後の1コマはトリスタンの出自を意識してのちょっとした小ネタなんでしょうが
さすがにキャプテンアレックスを「トリスタンと似てる」と言ってしまうのは
無理がある気がするなあ。
○ときた洸一「異説 真悪参伝」「異説 真悪参伝 白銀の章」
本書のラストを飾るときた洸一氏の『異説 真悪参伝』は
武者真悪参がナイトガンダムへとなる過程を描いた騎士と武者とを繋ぐ作品。
「武者真悪参が銀の楯を持ち出したところを雷に撃たれ
スダ・ドアカワールドへと転移して騎士ガンダムとなった」というのは
シリーズのかなり初期から存在する設定でこれまでにもいくつかの解釈がありましたが
武者真悪参・戦国伝側の事情をここまでガッツリ描いた作品は
意外にも本作が初めての気がしますね。
そして本作品はとにかく作画に力が入っており
悪夢から目覚めた真悪参の表情やサタンガンダムの姿、
「狂気」を軸にしたストーリー展開なども含めて
「自分のイメージするときた洸一先生」とは一味違う絵柄になっているのが印象的。
「コミックボンボン」での平成ガンダムのコミカライズ時代から
氏の作品には馴染みがありますが
ここに来て新たな一面を見せてもらった気がします。
前後編でページ数も多く名実共に本アンソロジーのメイン作品、といった感じですね。
後編で描かれたキュベレイと百式の関係などは
近年ネタにされがちな「シャアを追いかけるハマーン」そのままで何だか微笑ましいです。

ちなみにこちらの『異説 真悪参伝』は本書に収録された前後編で
物語としてはしっかり完結しておりますが
本書と同日発売の「月刊ヤングマガジン」には
騎士ガンダムがラクロアで試練を受けて
過去の過ちを乗り越える第3章「黄金の章」が収録されており
そちらも含めて押さえておきたいところ。
ヤンマガのほうにも付録でカードダスがついていたりと完全に抱き合わせ販売なんですが
悔しいけどやっぱり買ってしまうのです。
ところで本作では真悪参が湯飲みを持ってるシーンがあるんですが
どうやって飲んでるのかすごい気になる……気にならない?
というわけでこちらの『SDガンダムスペシャルアンソロジー』ですが
振り返ってみると作品ごとにけっこう方向性が違うというか
(1)SDガンダムへの思い入れを語るエッセイ&紹介漫画
(2)オリジナル作品にSDガンダムの要素をちょっと加えたもの
(3)既存のSD作品の外伝
の3つに大別出来るような気がしますね。
30周年のお祭り企画で講談社で活躍している作家さんが中心、という
大人の事情での縛りもあったんでしょうか
個人的には(3)のような外伝作品、クロスオーバー作品をもっと入れてほしかったですね。
SDガンダムはカードダスやプラモデルを中心に展開されており
物語にも隙間や考える余地がある作品が多いので
そこらへんを現代の作家陣がどのように解釈してどんなふうに埋めてくれてくれるのか、
というところをもっと大胆に見せてほしかった気もします。
どうせコアなファンしか買わないと思いますし。
ちなみに本コミックは限定カードダス7種つきで税抜2000円という価格ですが
カードダスが付属しない電子書籍版も販売されておりそちらは600円。
キラカード1枚200円と考えれば妥当な値段なのかなあ、と。
ところでほしの竜一氏の「騎士ガンダム物語」の電子書籍化が
前期シリーズ(聖騎兵物語)で止まってしまってるんですよね。
紙の本はガンダム騎士団まで全部復刊したので出せると思うんですけどね……。